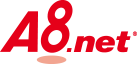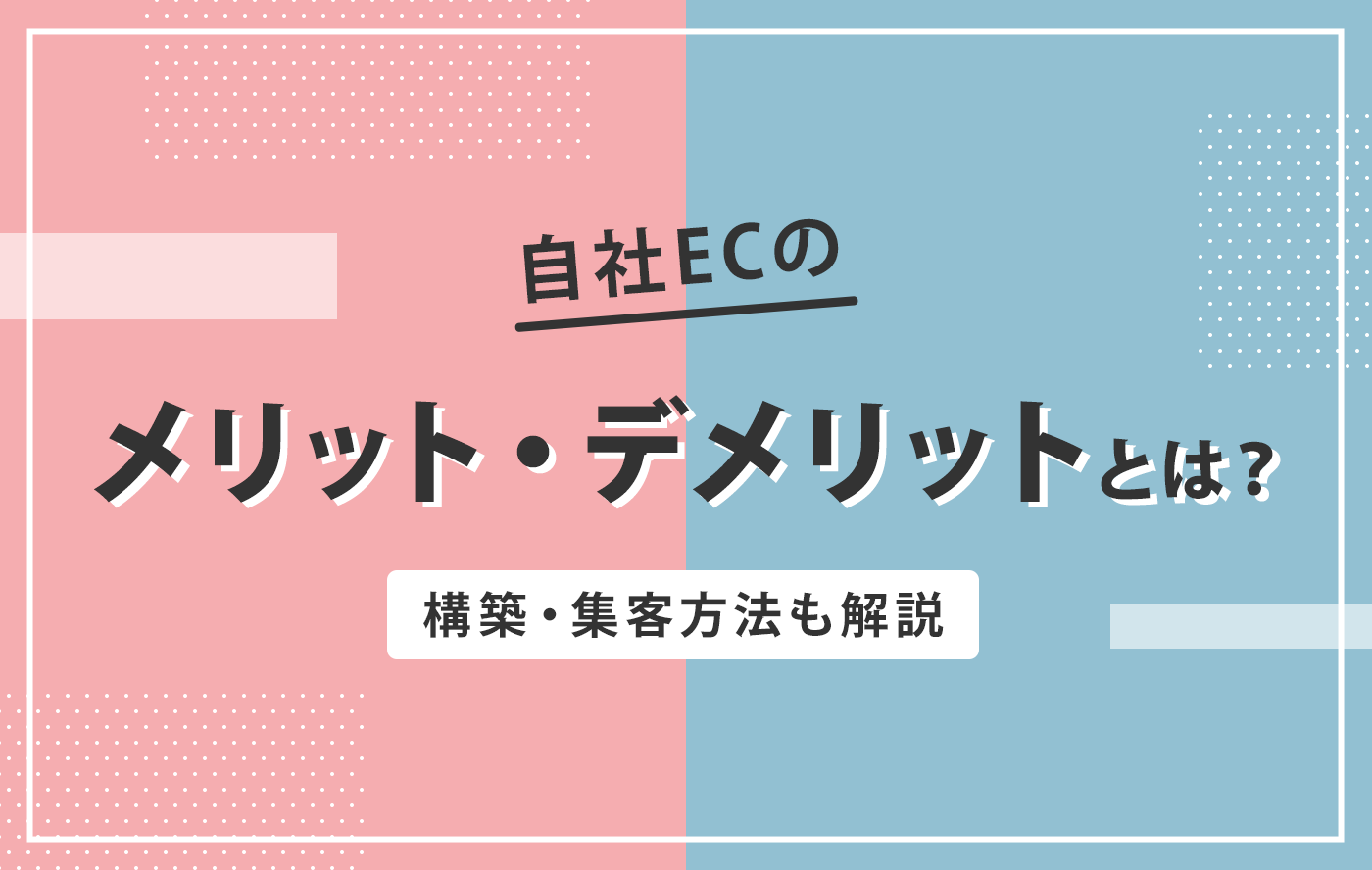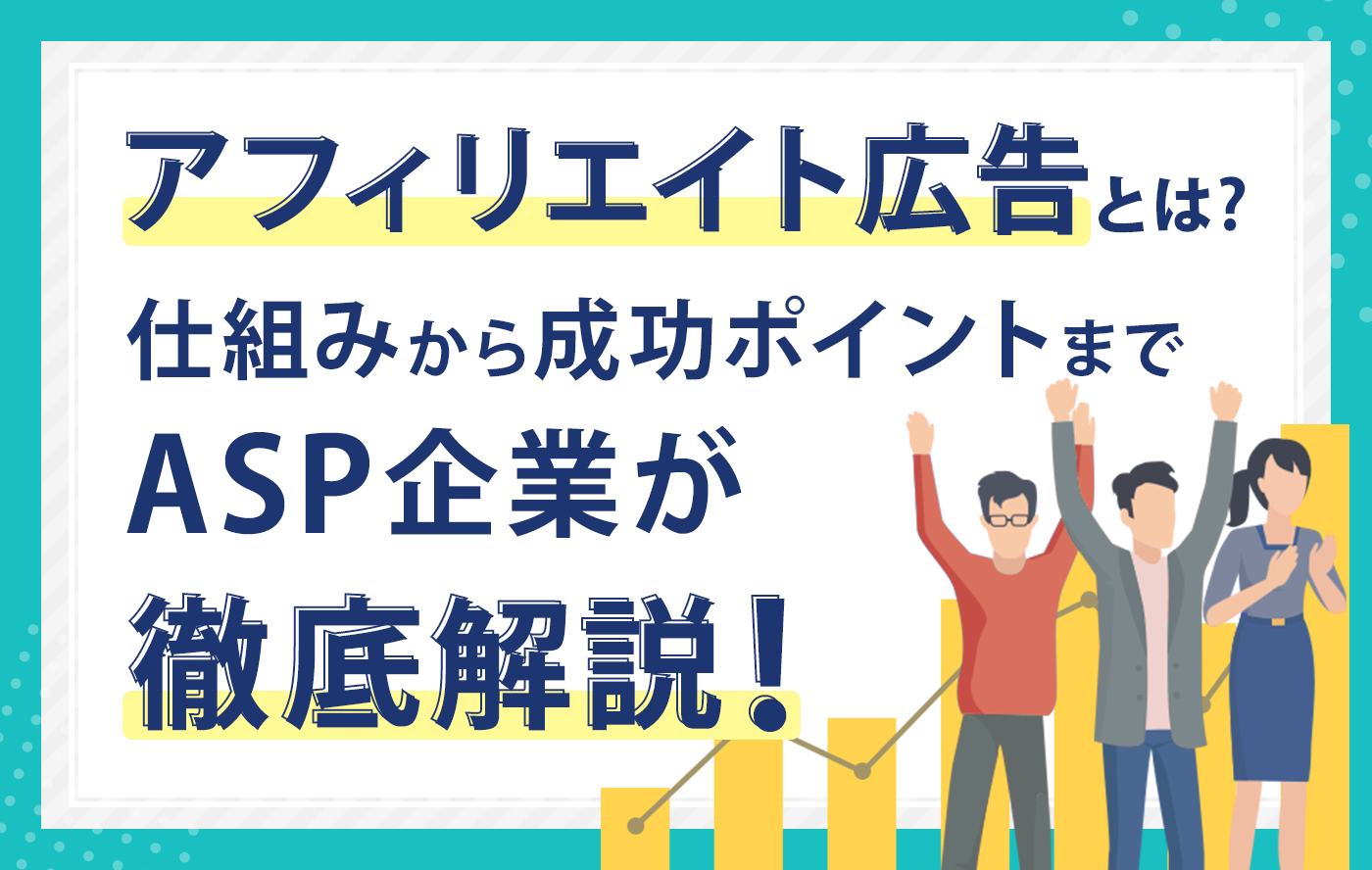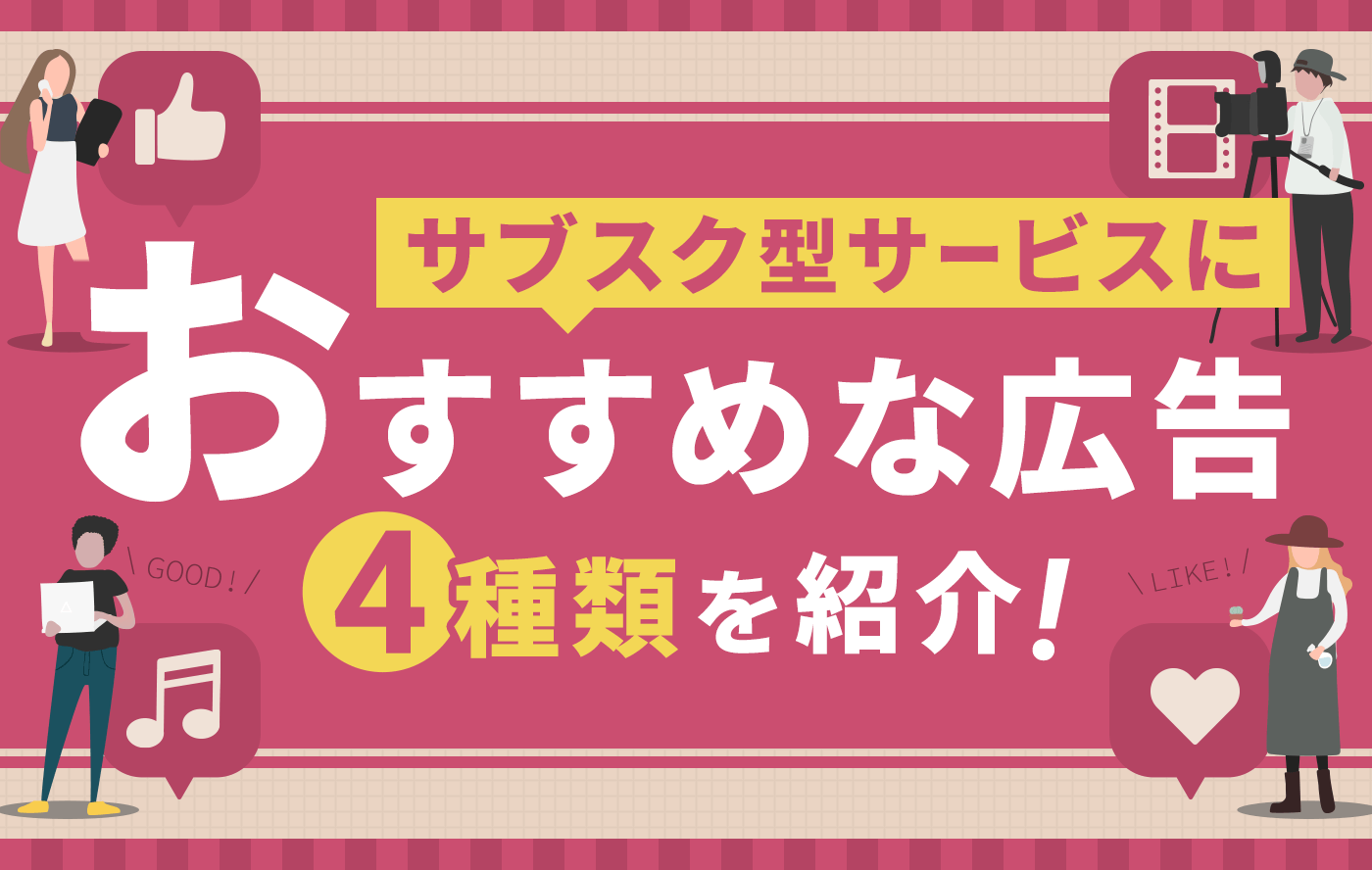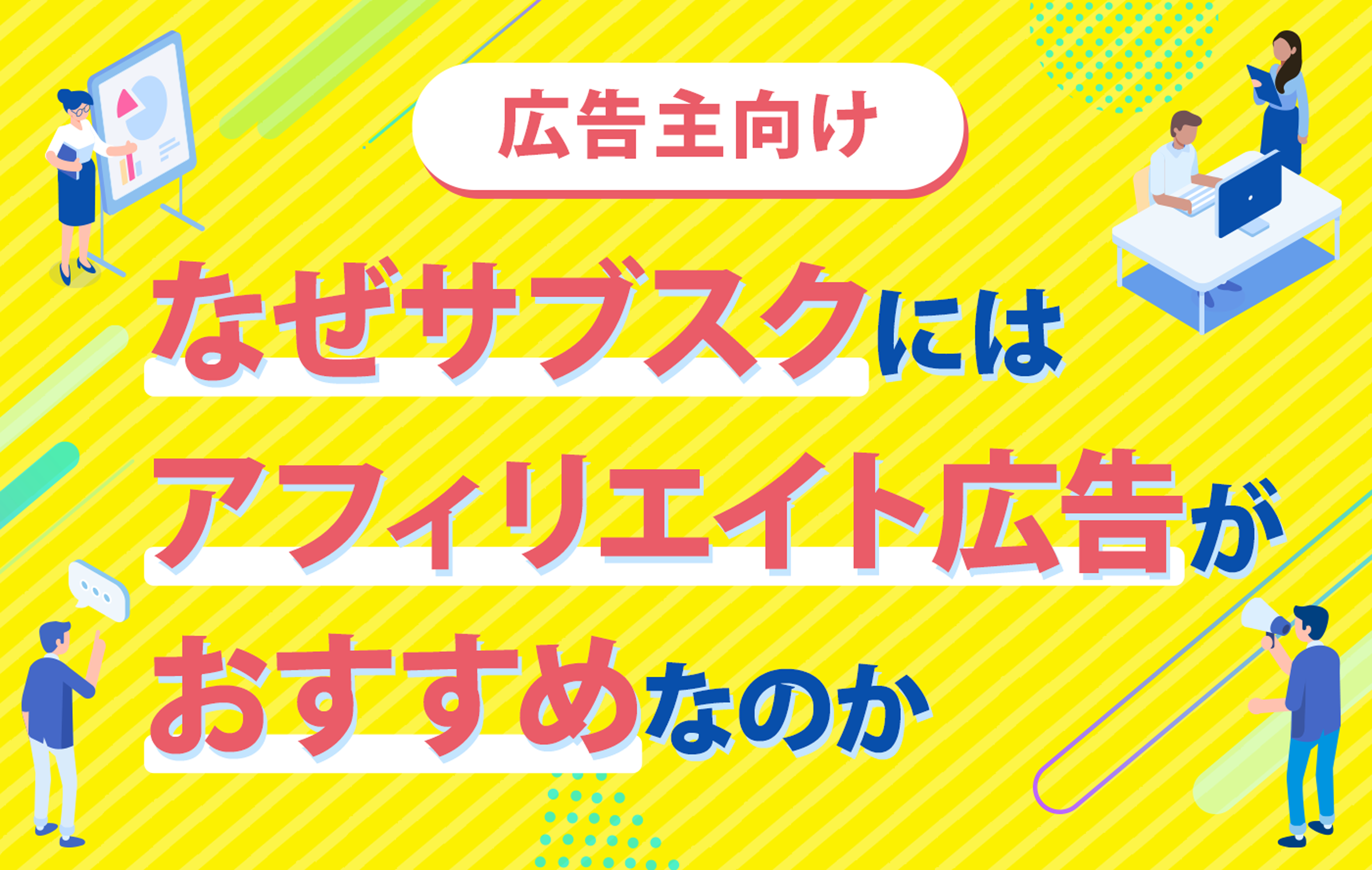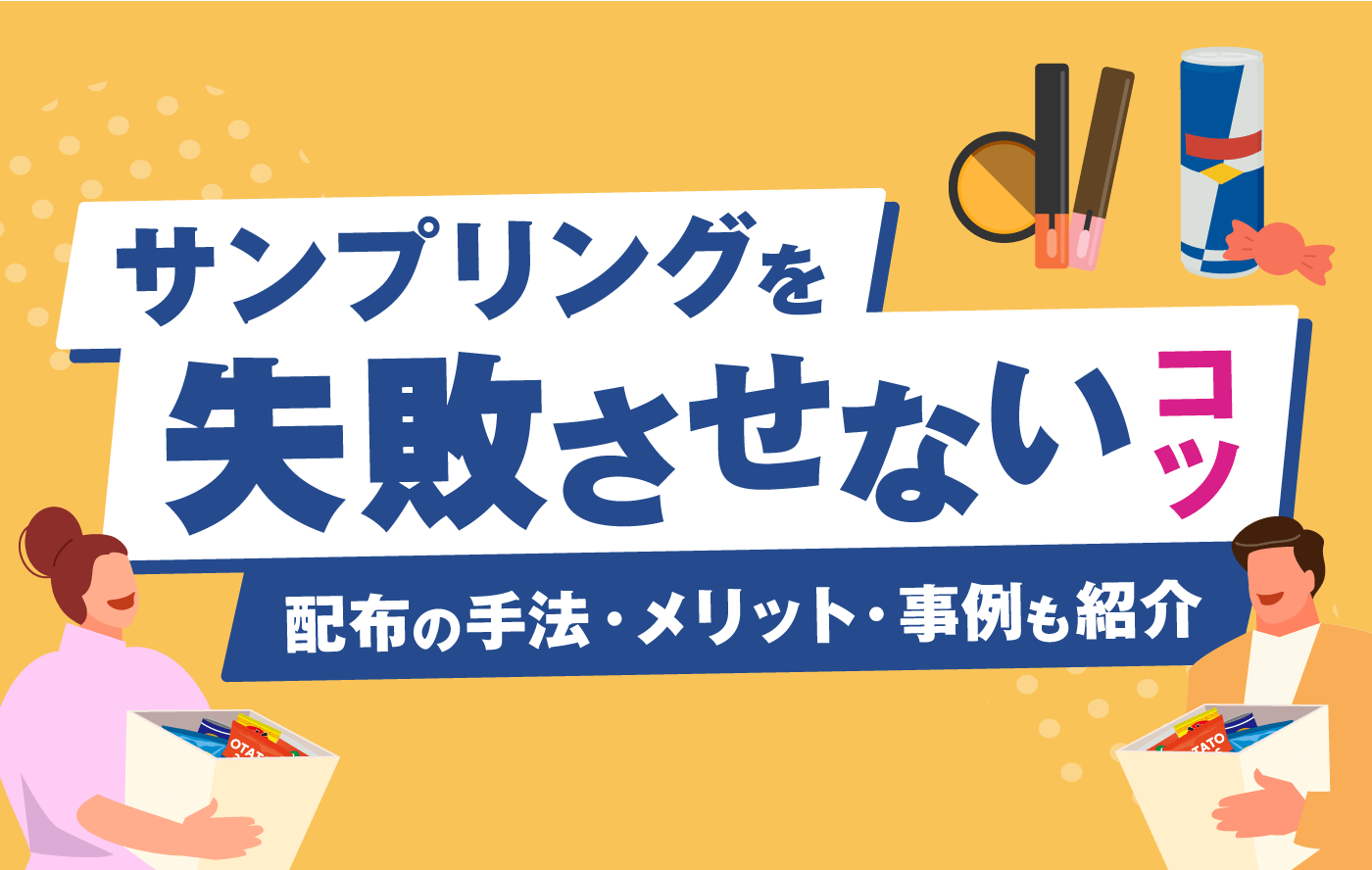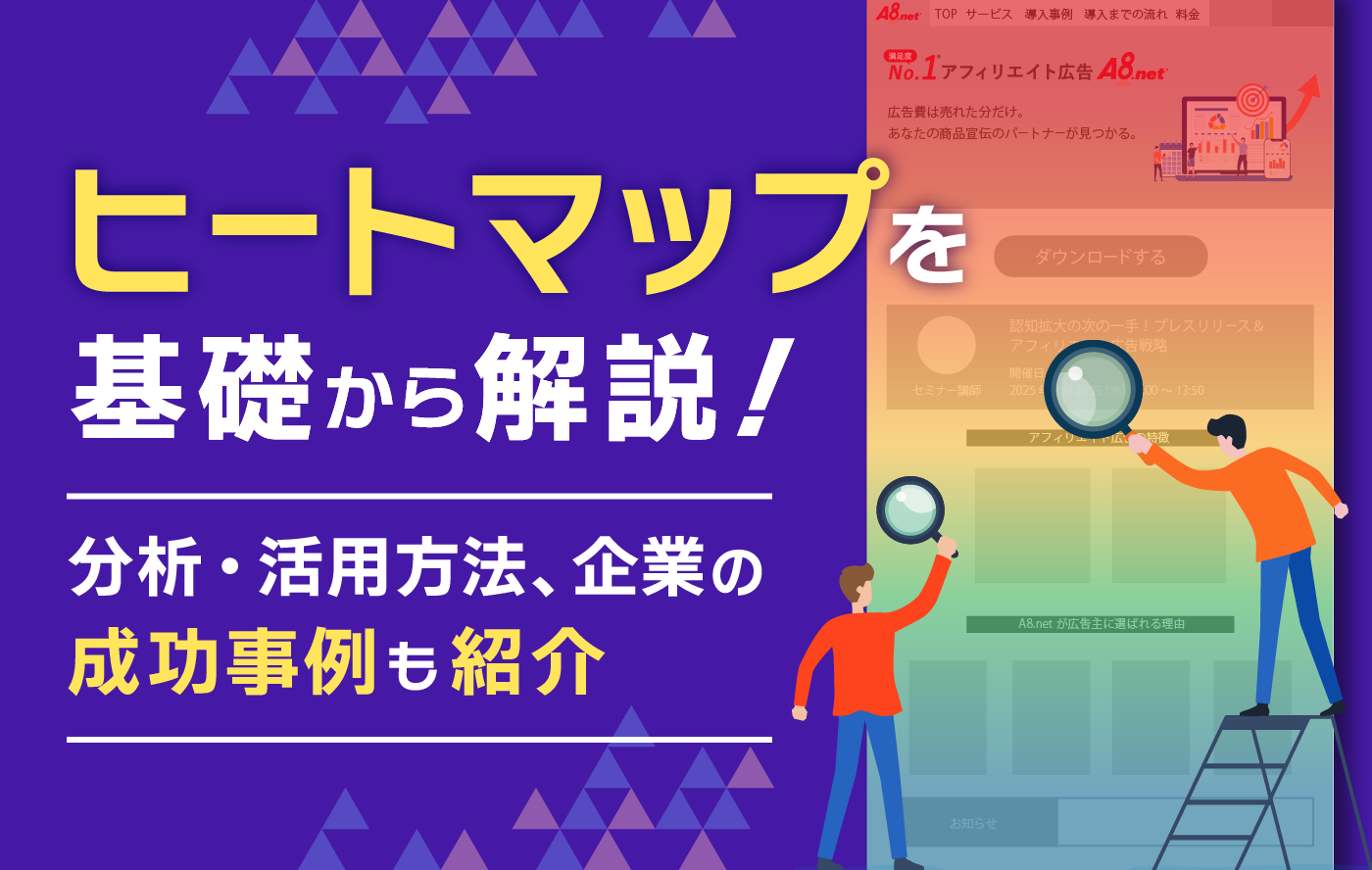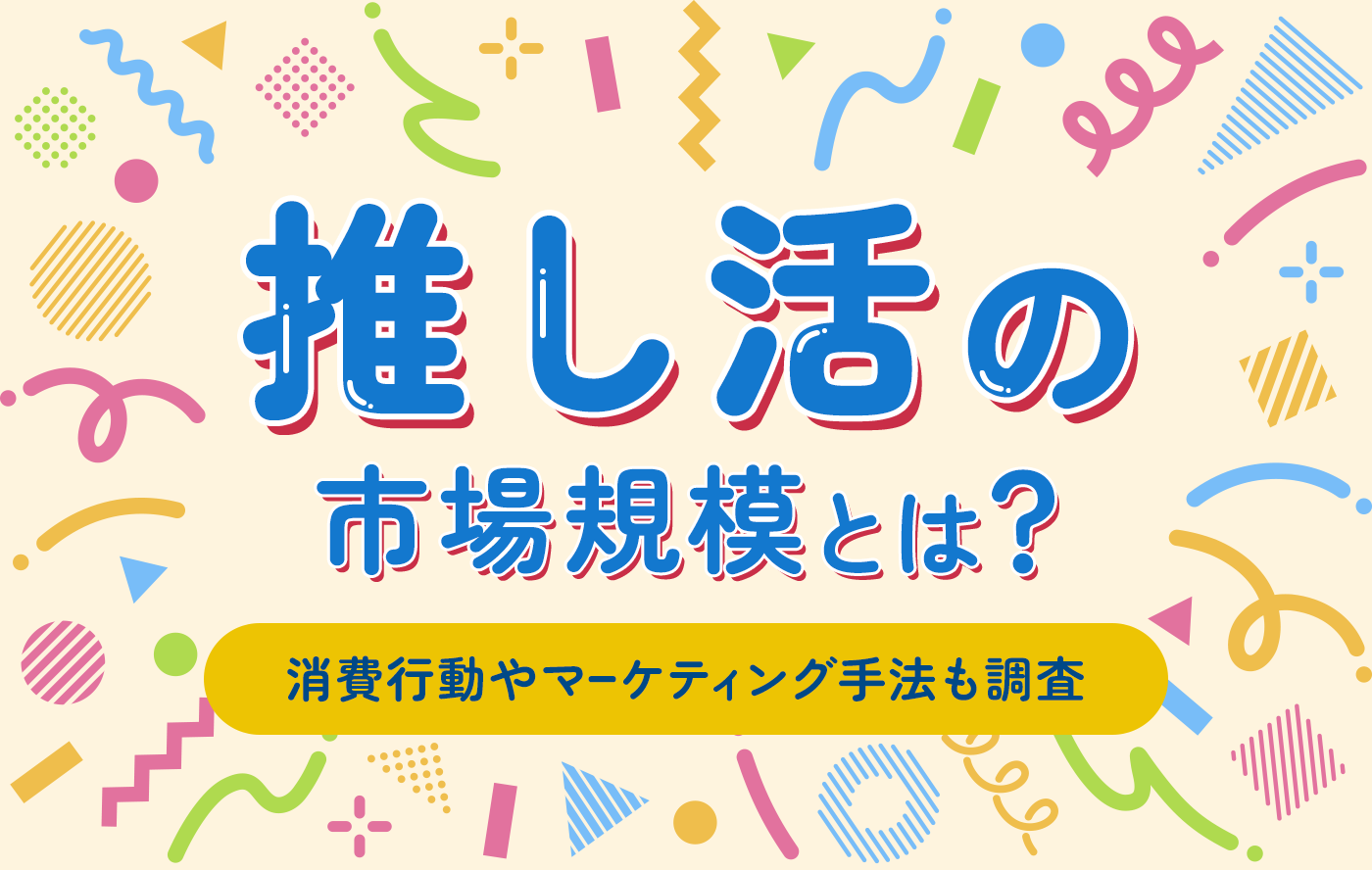現在、私たちの周りには数え切れないほどのサブスクリプションサービス(サブスク)が溢れています。
どのような種類があるか、あなたはご存知ですか?
このコラムでは新しくサブスクサービスを起業・開発したい担当者の方に向けて、 サブスクの事業モデル5種類の特徴や事例、関連する指標を解説しています。
「サブスクサービスの事業モデルはどのようなものがあるのか知りたい」
「サブスクサービスを起業する場合、どんな数値が重要なのか分からない」
といった方はぜひご覧ください。
サブスクの事業モデル5種類
では次に事業モデルとしてサブスクを分解してみましょう。サブスクの事業モデルは下記の5種類に分けられます。
会員制モデル
- 形態
- サービス利用型
- 代表例
- 動画・音楽配信サービス
オンライン英語学習など
会員制モデルは定額料金を支払ってサービスの会員になることで、サービスを利用できるモデルです。動画・音楽配信といったサービスはこれにあたります。世間一般で最もイメージされるサブスクの事業モデルではないでしょうか。
『NETFLIX』や『Apple Music』などを始めとした、「料金を支払えば使い放題でサービスを受けられる」という点は会員ユーザーにとって非常に明快で、複雑な料金設定が忌避される昨今において支持されています。
インターネットを利用したサブスクサービスの多くが会員制モデルの形式を取っており、どの業界でも転用しやすいことも特徴です。初回1ヶ月間の料金を免除して新規ユーザー獲得を促進するケースもよく見られます。
定期購入型モデル
- 形態
- 購入型
- 代表例
- Amazon、楽天などの定期便購入
食材宅配サービスなど
定期購入型モデルはユーザーに特定の商品を販売する購入型のモデルです。取り扱っている商品はサプリメントやコンタクトレンズ、雑誌や新聞など日常的に使用する商品が多いです。
『Amazonの定期おトク便』では数万点の対象商品の中から商品を選択し、数量・配送頻度を選択して注文することが可能です。また、複数の商品をまとめて定期注文することで5~15%程度の割引が適用されます。
ユーザーにとっては定期的な購入の手間を省いて安く購入することができ、企業側としても商品の在庫消費や売上目標の設定が立てやすくなるので、両者にとってメリットが大きいモデルと言えます。
レコメンドモデル
- 形態
- 購入型・サービス利用型どちらもあり
- 代表例
- ファッションレンタル
ワインの定期お届けサービスなど
レコメンドモデルはユーザーの趣味嗜好や生活環境などに合わせて、専門家やAIからのおすすめ商品を提供するモデルです。食品やファッション、フィットネスなど好みが分かれやすいジャンルで利用されています。
例えば、ファッションレンタルサービスの『airCloset』では、ユーザーからの無料診断の結果をもとにプロのスタイリストがセレクトした洋服が自宅に届くサービスを展開しています。届いた品物には着こなしのアドバイスも入っているので「似合う服が分からない」「いつも同じ服装になる」といった方にはぴったりのサービスでしょう。
レコメンドモデルのサービスは複数回の利用を重ねていくことで、ユーザーの好みを蓄積し最適な商品を提案する精度が上がっていきます。精度が高ければ高いほどユーザーの信頼を獲得し、長期的な収益に繋げていくことが可能になります。
頒布会(はんぷかい)モデル
- 形態
- 購入型・サービス利用型どちらもあり
- 代表例
- 花の定期便
化粧品詰め合わせお届けサービスなど
頒布会モデルは、企業側で毎回異なる商材をセレクトして届けるモデルです。
レコメンドモデルに近いようにも思えますが、明確な違いはユーザー側から商品の選択が任せられており、選択権が企業側にあるという点です。化粧品や雑貨、食品といった多種類な商材、ユーザー側での選択が難しい商材などで利用されています。
例えば、花のサブスク『+hana(タスハナ)』では国産の様々な品種の花を自宅に届けるサービスを展開しています。商品は色や形が揃っていないものや、試作品種など美しく新鮮なものの行き場を失ってしまった花を活用しており、ユーザー側は「なにが届くかわからないワクワク感」を感じる事ができます。
企業側は商品の選択権を保持していることで在庫管理がしやすく、利益率を調整しながら運用することが可能となります。
オフライン連動モデル
- 形態
- 購入型・サービス利用型どちらもあり
- 代表例
- 定額制コーヒー飲み放題サービス
焼肉食べ放題サービスなど
最後はやや変わり種となりますが、オフライン連動モデルというものも存在します。
オフライン連動モデルはその名の通りオフライン=つまり店舗などのリアルな場所でサービスを受けられるモデルです。特にカフェやレストラン、居酒屋といった飲食店などでの活用が見られます。
牛丼チェーンすき家では、使用期間内であれば何度でも対象商品が70円引きとなる『Sukipass』を税込200円で販売しています。手軽な料金設定、3回で元が取れるお得感が人気となっています。
このように店舗でもチケットのような形でサブスク化が可能なことは非常に魅力的です。企業側はユーザーの来店回数を増やすことで長期的な利益に繋がりやすくしています。
サブスクリプションビジネスに関係する重要な指標と単語
サブスクリプションビジネスを成功へ導くうえで、重要な指標と単語を説明します。
- Churn Rate(解約率)
- RPM(定期利益率)
- ARPU(ユーザー平均単価)
- LTV(顧客生涯価値)
- カスタマージャーニー
Churn Rate(解約率)
Churn Rate(チャーンレート)は、「解約率」を表す指標です。
毎月安定した新規顧客を獲得が出来ていたとしても、解約が多いと安定した収益を得続けることはできません。
サブスクリプションビジネス以外でも解約の防止策を講じることは必要です。そのために、サービスの改善や新しいコンテンツを提供していくことが重要になります。
なお、サービスによっては退会率や離脱率と表現されることもあります。
また、Churn Rateは【月間の合計解約ユーザー数÷月初のユーザー数】で算出され、月初にいる利用者のうち、月末までにどれくらい解約してしまったのかを表します。
- 業界別チャーンレート
-
アメリカの調査によると、デジタル関係業界のアベレージは6.63%、業界全体のチャーンレートのアベレージは7.02%です。
産業ごとだと、SaaSのアベレージは4.90%。BtoBのSaaSビジネスにおけるチャーンレートの理想は、3.0%未満であるとされています。
ユーザーのサポートを重視し、サービスを継続してもらうことで、サブスクリプションビジネスは成功の一歩を踏み出すことができます。
RPM(定期利益率)
RPM(Recurring Profit Margin)は、「定期利益率」です。
1年間の収益(ARR)や月の収益(MRR)から解約により無くなる売上と定期費用を引き、売上に占める利益の割合を算出します。
売り切り型のビジネスは、売上に連動する変動費(商品原価)、連動しない固定費(管理部門の人件費や賃料など)として区別しますが、サブスクリプションビジネスにおいては、定期利益しかないため、区別することができません。研究開発費も既存ユーザー保持のために使われるため、定期(費用)として計上します。利益率向上が重要です。
算出方法は以下になります。
RPM= ( ARR – ( Churn + 売上原価 + 研究開発費 + 一般管理費 )) ÷ ARR
ARPU(ユーザー平均単価)
ARPU(Average Revenue Per User)は、ユーザー1人あたりの平均収益を表す指標です。
直訳すると、「ユーザー平均単価」です。
主に、サブスクリプションビジネスで使われているKPIですが、ゲーム事業の企業業績を評価する指標として行き渡っているようです。
算出方法は以下になります。
ARPU=月の収益(MRR) ÷ ユーザー数
また、似た指標で、ARPAとARPPUがあります。
- ARPA
-
ARPA(Average Revenue per Account)は、1アカウントあたりの平均売上指標です。
ARPUとの違いは、1アカウントあたりの売上を求める部分です。ユーザー数より、アカウント数で課金することが多いSaaSモデルのビジネスにおいて、複数端末で利用されることが多いことから、事実に近い数値を把握できます。
算出方法は以下になります。
ARPA=月の収益(MRR) ÷ アカウント数 - ARPPU
-
ARPPU(Average Revenue per Paid User)は、課金ユーザー1人あたりの平均課金額指標です。ARPUとの違いは、課金1アカウントあたりの課金額を求める部分です。主に、無料プランがあるBtoB向けのSaaSビジネスで活用されています。
事実を正確に把握し、収益向上を図るために、課金ユーザーを対象としたARPPUの活用が効果的です。
算出方法は以下になります。
ARPPU=月の収益(MRR) ÷ 課金アカウント数
LTV(顧客生涯価値)
LTVとは「Life Time Value」の略称で、直訳をすると、「顧客生涯価値」になります。
顧客が、取引を開始してから終了するまでの間に、自社に対してどのくらい利益をもたらしたか、収益の総額を算出するための指標です。サービスや商品への愛着が高いほど、LTVは高まると言われています。
顧客がサブスクリプションを登録してから解約するまでの支払総額になるため、LTVが高い場合は、長い間サービスを利用してくれているという意味にもなります。
解約をせずにサービスを使い続けてもらうために、カスタマーサクセスの考えと合わせて重要視する企業は増加傾向にあります。
計算式は以下になります。
LTV=収益率×購買頻度×継続購買期間×平均購買単価
カスタマージャーニー
カスタマージャーニーとは、サービス購入の過程と意思決定までのストーリーを「見える化」する手法のことを指します(直訳すると、「顧客の旅」)。
「見える化」を行うことで、アップセルの推奨や適当なカスタマーサポートをすることができます。
なお、サブスクリプションビジネスに限らず、カスタマージャーニーは重要な指標になります。マーケティングオートメーションツールやテクノロジーの発達により、カスタマージャーニーへの注目が高まっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本コラムではサブスクリプション(サブスク)の事業モデルや特徴について紹介させていただきました。
サブスクは様々な業界で活用できるビジネスモデルであり、中小企業やスタートアップ企業も大きく飛躍できる可能性があります。
そのためにはあらかじめ成功のポイントや事例を把握しておくことが重要です。
以下のコラムでは成功事例なども交えて具体的に紹介しています。気になる方はぜひご覧ください。